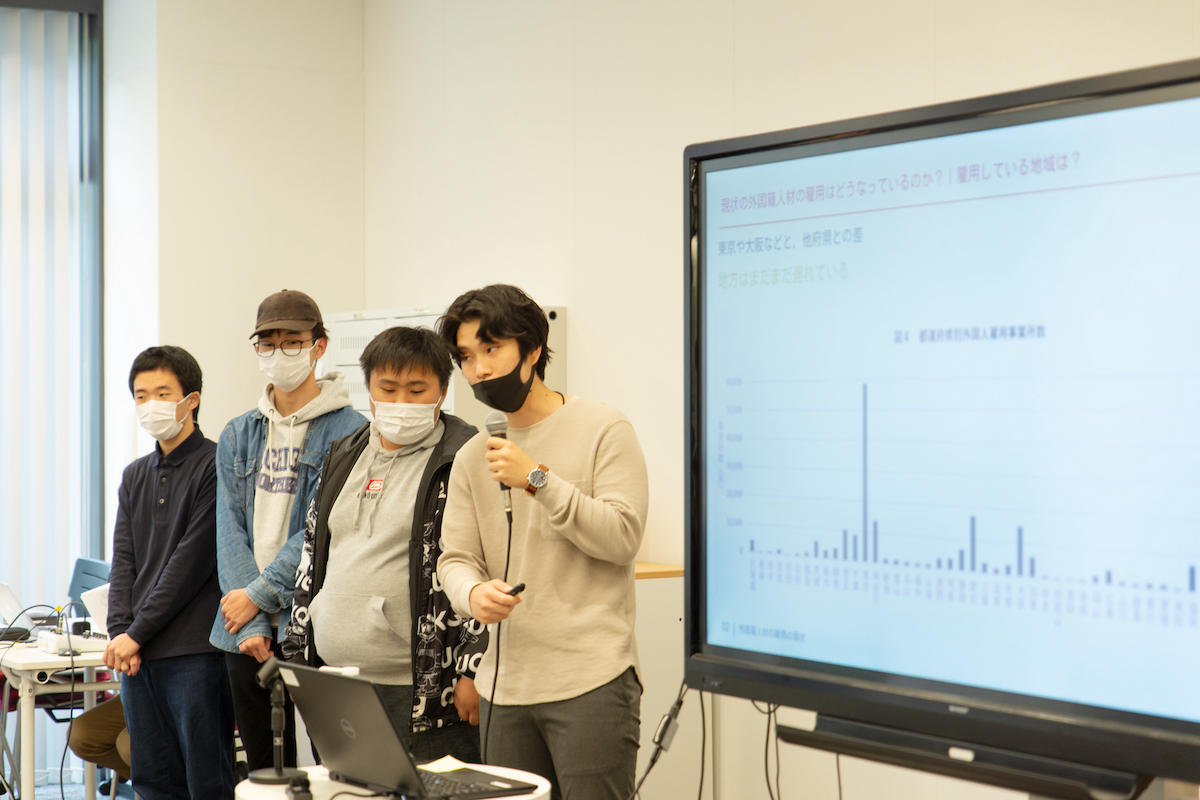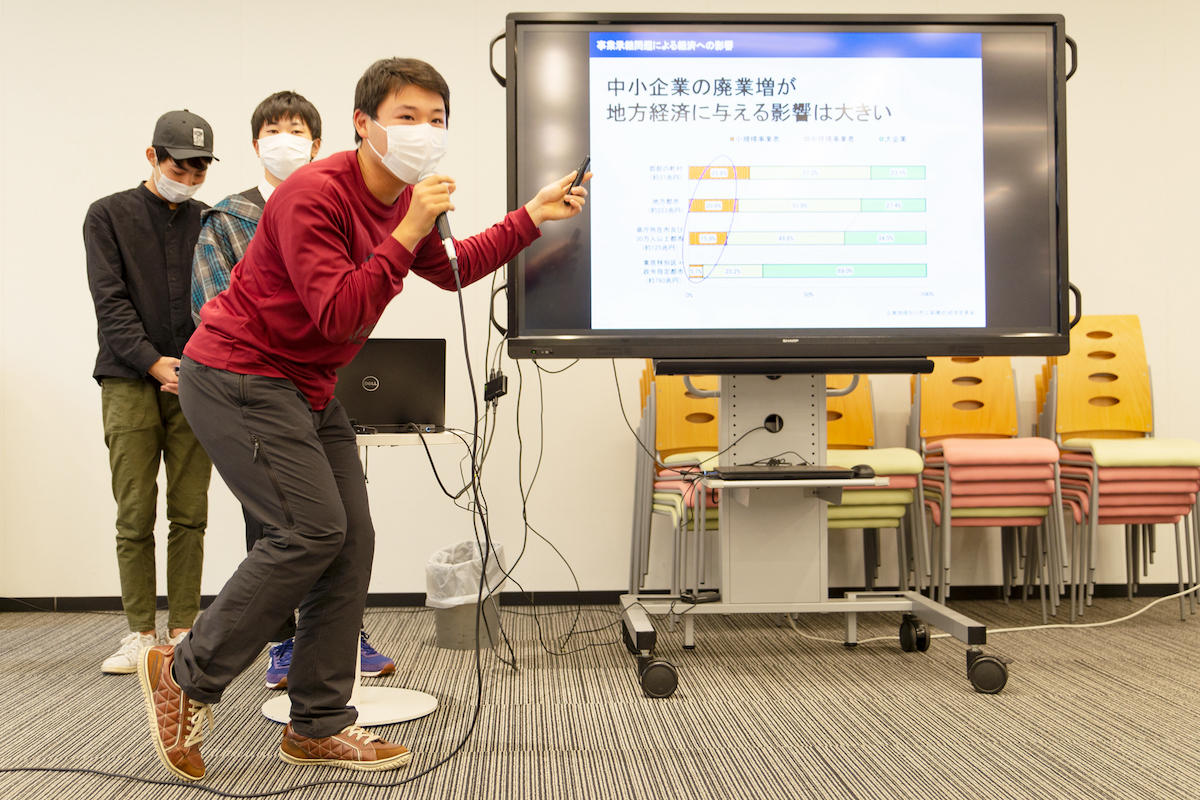久留米工業大学
新着情報
2021.12.14『地域連携 I 』成果発表会を開催!地域の新たな流れを感じたイベント
2021年12月1日、久留米工業大学にて『地域連携I』の成果発表会が開催されました。
『地域連携I』とは、地域の社会人と大学生がクラスメイトになり、一緒に課題解決に必要なスキルを学び磨く地域に開かれた講座です。
約4ヶ月に渡る講座を乗り越え、約2ヶ月かけて地域に実在する課題をテーマに、社会人と大学生の混成チームが本質的課題から解決アイデアまで考え抜きました。
約半年間の集大成となる成果発表(本質的課題〜解決アイデア)を、地域の企業経営者、社会人、行政、銀行、教授、学生、住民の方が一緒に聞きました。
チームAは、久留米市の水害被害問題に挑みました。令和2年6,7月の久留米市の水害被害額は約16億円。たった2ヶ月でこれだけの被害状況です。
チームAは、大雨を防ぐことは難しいので、水害被害の軽減施策を考えてきました。それは約3,000年前から南米ボリビアで行われてきた水害に強い伝統農法「カメジョネス」、盛り土です。
日本におけるカメジョネスの水害に対する効果を示すレポートは見つからなかったそうですが、実際に実験してみたところある程度の効果は見られたようです。現実的にできそうな方法であり、実際に農家さんに協力を依頼し、実験した点は驚きです。
チームBは、地方を久留米市と定義し、久留米市における中小企業の事業承継問題に挑みました。地方経済における中小企業の売上構成比は全体の約7割です。中小企業が廃業していくことは、特に地方にとって大きな打撃となります。
チームBは、事業承継されないことの最大の問題は、企業資産(技術やノウハウなど)が失われることにあると示し、地域が持続可能になるために、企業資産を地域に残していくことが重要だと訴えました。
そこで提示された施策が「ローカル版オープンイノベーション」。久留米市の企業から、久留米市の企業へ、資産が受け継がれていく仕組みを、マッチングサイトだけでなくオフラインでのサポートを組み合わせた図を使って発表しました。
チームCは、日本が抱える人手不足問題と外国籍人材の雇用が進まない問題に挑みました。国内人口が減少し市場が(一部を除き)縮小傾向にあるとはいえ、さまざまな業界で恒常的な人手不足が続いています。日本政府が外国籍人材を積極的に受け入れようとしている動きからも、外国籍人材の力は必要だということが現在の日本の判断です。
チームCは、外国籍人材の雇用が進まない問題の本質的な課題は、言語の壁などではなく、企業側が外国籍人材を雇用する明確なメリットを感じていないからだと結論づけました。
明確なメリットを言葉で伝え腹落ちしてもらうことは難しいと考え、外国籍人材の雇用数を増やすという目的達成のために、まずは外国籍人材を雇用している企業がさらに雇用を増やす方向で施策を検討しました。
チームC_日本が抱える人手不足問題と 外国籍人材の雇用が進まない問題.pdf
チームDは、規格外野菜問題に挑みました。日本は年間約600万トンの食品ロスをしており、消費者の手まで届かず処分されてしまうこともある規格外野菜は農作物生産量の約3〜4割だそうです。
チームDは、この問題の本質的課題は、大量の規格野菜を取りまとめるJAのような存在が、規格外野菜にはいないことだと発表しました。
規格外野菜は、集める側も生産側も、手間の割にお金にならないため、あまり手をつけないとか。解決方法は、規格外野菜専門店を立ち上げることです。定期的に規格外野菜を収集し、店舗での販売や卸売りをしていきます。まずはマルシェなどのイベントから小さく始めて認知度上げていくそうです。
『地域連携 I 』の成果発表会では、地域の企業の方を審査員に迎え、久留米工大の教員含めて3名で最優秀チームを決めています。今年は、株式会社未来工房 取締役 金原氏、株式会社サンカクキカク 取締役 浅沼氏、そして久留米工大 AI 応用研究所 副所長 小田教授が審査員でした。
審査は、独創性・市場性・将来性・プレゼン資料の分かりやすさ・聞きやすい発表か、の5つの視点で行われました。
最優秀チームは、規格外野菜問題に挑んだチームDでした。
質疑応答で規格外野菜を売ると、規格品が売れなくなるのではないかという質問がありました。それに対して、規格外野菜は小さい規模で既に売られていますが、現状規格品への影響はないと回答。さらに、現状農作物の生産は規格外野菜ができることを想定し、30〜50%増しで生産されている点に言及し、規格外野菜もすべて売れ、生産した分が100%売れれば、トータルの利益はそれほど変わらないのではないかと付け加えました。
納得感のある空気が会場に流れた瞬間でした。
(写真:会場に笑いが響き続けたプレゼンターのプレゼンテーションの様子)
地域の社会人と久留米工大生が一緒に課題解決に必要なスキルを学び、地域の課題について真剣に向き合い考え続けた半年間。世代や肩書き、職種を超えて連携し、地域のさまざまな登場人物に現状分析と解決策を聞いてもらうことができました。
「もっと連携したいが、連携の仕方が分からない」というお声を地域でよく耳にします。「この取り組み応援しているよ」と、お伝えいただける回数が増えてきました。地域に新しい風が吹き始めているのかもしれません。
来年も『地域連携 I 』は実施予定です。参加希望の方は、久留米工業大学までお気軽にお問い合わせください。
▼お問い合わせはこちら▼
総務課(本館2F)
0942-22-2345(代表) FAX:0942-21-8770
E-mail:somukikaku@kurume-it.ac.jp
取材者:高田樹彦
久留米工業大学 広報コーディネーター
株式会社サンカクキカク 企画営業部 / 新規事業開発部 / 広報PR部 マネージャー