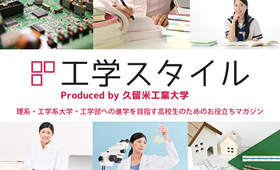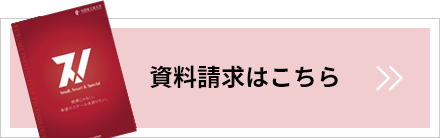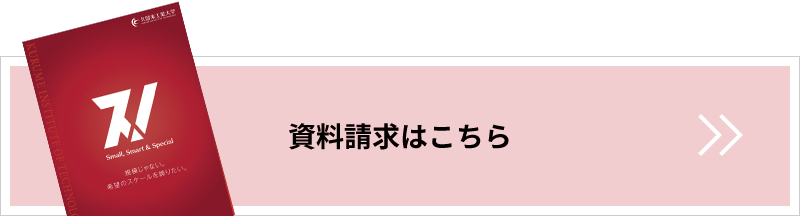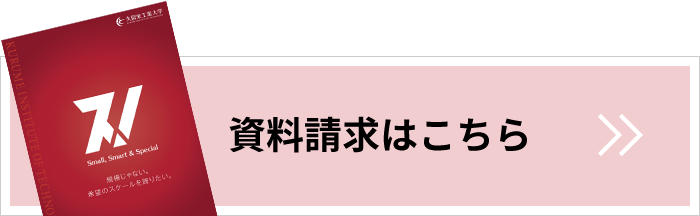高齢化社会において、介護や福祉に関する職種はますます需要が高まっています。しかし介護業界で働くには、介護や福祉に関する正しい知識を身につけておくことが求められます。
介護や福祉だけでなく、医療や建築の視点も加えて適した生活環境をアドバイスするのが福祉住環境コーディネーターです。
この記事では、福祉住環境コーディネーターの仕事内容や資格の概要、将来性などについて詳しく解説します。
目次
福祉住環境コーディネーターとは?

福祉住環境コーディネーターとは、高齢者や障がい者に対して安全に、そして快適に暮らすための住環境を提案するアドバイザーです。
年を重ねたり介護が必要な状態になったりして体を自由に動かすのが難しくなると、それまでの住環境に不便を感じやすくなります。
日常生活に支障が出ないよう、体の状態に合わせた住環境の整備をサポートする仕事です。
福祉住環境コーディネーターとして働くには、東京商工会議所が認定する民間試験に合格しなければいけません。
福祉住環境コーディネーター資格は1級から3級までの3つの級があり、試験に合格すると福祉住環境コーディネーターの名称で働くことができます。
福祉住環境コーディネーターの主な仕事内容
高齢化社会へと早いスピードで進んでいる現在、福祉住環境コーディネーターは介護や福祉、建築といった業界で求められています。
福祉住環境コーディネーターの仕事内容は、主に次の3つです。
1. 住宅改修のアドバイス
2. 福祉用具や介助用具の選定アドバイス
3. 住宅改修費支給申請の理由書作成
1.住宅改修のアドバイス

高齢者や障がいを持つ人に対し、安全で快適な住環境を整えられるようアドバイスします。
たとえば玄関土間と廊下、廊下と居室の段差をなくし、車いすや杖をついた状態でも本人が移動しやすいバリアフリープランを考えます。
浴室やトイレなどは立ち座りがしやすいよう壁に手すりを設置する、家族の介助を考慮して開き戸から大きく開く引き戸に交換するといった提案も多いです。
こうした提案は福祉住環境コーディネーターが独自に行うのではなく、ケアマネージャーなど本人の体の状態を把握している福祉の専門家と連携して行います。
2.福祉用具や介助用具の選定アドバイス

自宅で高齢者や障がい者が自分で移動や動作ができるようサポートする用具が数多く開発されています。
福祉用具や介助用具には、車いすや歩行補助杖など本人が使用する用具、介護用ベッドや床ずれ防止用具など介助作業をサポートする用具、スロープや手すりなど住宅に設置して使う用具などがあります。
本人が安全に日常生活を送れるよう、本人の体の状態に合わせて多くの種類から適した用具を選ぶのも福祉住環境コーディネーターの重要な仕事です。
3.住宅改修費支給申請の理由書作成

住宅改修費支給申請とは、在宅の要支援1または2の認定を受けた人が日常生活で必要とする住宅改修の工事を行う際に、改修が必要と認められれば自治体から改修工事費が支給される仕組みです。
手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止、扉の交換、便器の交換などの対象種目があります。
福祉住環境コーディネーター2級以上を所有していれば、住宅改修費支援申請時に必要な理由書を作成するサポートが可能です。
福祉住環境コーディネーターになるには
介護・福祉業界だけでなく建築業界でも活躍できる福祉住環境コーディネーターは、社会的ニーズが高まっていることもあって将来有望な職種です。
活躍できる福祉住環境コーディネーターになるには、次のような方法がおすすめです。
2級以上の資格を取得する

福祉住環境コーディネーターになるには、福祉や介護、建築など多角的な視点からの専門知識をつけるためにまず資格試験に合格することが必要です。
福祉住環境コーディネーターの資格は1級から3級までありますが、2級以上の資格取得をめざしましょう。
2級以上を持っていると就職時に強い武器になるだけでなく、入社後に資格手当が支給されるなど優遇される可能性があります。
さらに、介護保険の介護予防住宅改修費支給申請において必要な書類である理由書が作成できるのでおすすめです。
コミュニケーションスキルを高める

住環境を整備する目的は、高齢者や障がい者が自宅でできるだけ自立した日常生活を送れるようにすることです。
その実現のためには、利用者が本当に必要としていることは何か、どのように生活したいのかという要望を把握して整備の内容を的確に提案しなければいけません。
正確なヒアリングをするために、相手の話をしっかり聞いて不明な点は質問できる、相手が悩みを気軽に相談できるようなコミュニケーション力を身につけておくと有利でしょう。
福祉関連の学校に通う

福祉住環境コーディネーターは、医療や福祉、介護、建築などさまざまな知識を身につける必要があります。
資格取得だけが目的であれば独学でも勉強は進められますが、専門知識だけでなく業界や現場についても熟知している講師から直接レクチャーを受けておくと福祉住環境コーディネーターの存在意義や働き方がイメージしやすく、就職後の業務もスムーズに始められるでしょう。
より体系的に知識を身につけるためには、介護や福祉系の学科がある大学や短大、専門学校に通うのがおすすめです。
福祉住環境コーディネーターの資格を取得するメリット
福祉住環境コーディネーターは、高齢者や障がい者が自宅で自立した生活を送るためのサポートをする専門性の高い仕事です。
資格を取得すると、専門知識を身につけられる以外に次のようなメリットがあります。
幅広い業界で活躍できる

福祉住環境コーディネーターとして働ける場は数多くあります。
医療業界であれば病院や保健所やリハビリテーションセンター、介護・福祉業界であれば老人保健施設や福祉用具センター、建築業界であれば工務店やハウスメーカーなどです。
さらに自治体の福祉相談窓口や社会保険関連の窓口など、行政の立場から住環境整備のアドバイスをすることもできます。
どの分野の立場からアドバイスするかによって選択する業界は異なりますが、就職時の選択は多くさまざまな業界で活躍できるでしょう。
利用者の生活環境をよりよいものにできる

住環境の現状の問題点を整理し、改善のアドバイスをすることで、高齢者や障がい者など介護を必要とする人はより快適に生活できるようになります。
移動する際の転倒リスクが下がると安全に暮らせますし、お風呂やトイレも使いやすくなってストレスが減少します。
自分でやってみよう、外出してみようといった意欲が生まれるきっかけになり、心身の健康に繋がる可能性も高いでしょう。
高齢者や障がい者が笑顔で生活できるためのお手伝いによって、大きなやりがいを感じられる仕事なのです。
福祉住環境コーディネーターの資格の概要
幅広い業界で活躍できる福祉住環境コーディネーターになるには、資格を取得するのがおすすめです。
福祉住環境コーディネーター資格の概要についてまとめましたので参考にしてください。
福祉住環境コーディネーター試験の概要

福祉住環境コーディネーターの試験は、受験資格の制限がありません。
そのため年齢や性別、国籍、学歴を問わず誰でも受験可能です。
2019年度に3級および2級を受験した人の業種を見ると、医療業や社会保険・社会福祉、建設業、製造業などさまざまな業種の人が受験しています。
また福祉用具専門相談員や介護福祉士、看護師、建築士などの資格を所有している人が受験しており、専門性の強化を目的としている人も多いことが分かります。
受験はもっとも難易度が低い3級から挑戦するパターンが多いですが、2級からの受験や2・3級の併願も可能です。
なお1級は2級に合格した人のみが受験できます。
福祉住環境コーディネーター試験の範囲

福祉住環境コーディネーター試験の範囲は、3つの級それぞれで異なります。
試験で問われる内容や試験形式、受験料等の詳細を級ごとに解説します。
3級
公式テキストの内容が出題範囲です。
少子高齢化社会と共生社会への道、福祉住環境整備の重要性や必要性、在宅生活の維持とケアサービス、高齢者の健康と自立、バリアフリーとユニバーサルデザインの考え方、生活を支える支援用具、住まい整備のための基本技術、ライフスタイルの多様化と住まいなどの内容に関連した問題が出題されます。
解答はマークシート方式で試験時間は2時間、100点中70点以上で合格となります。
受験料は4,400円(税込)です。
2級
3級の内容および公式テキストの内容が出題範囲です。
高齢者・障がい者を取り巻く社会状況と住環境、福祉住環境コーディネーターの役割と機能、障がいのとらえ方、リハビリテーションと自立支援、福祉住環境とケアマネジメント、福祉住環境整備の共通基本技術や実践に必要な基礎知識、生活行為別に見た福祉用具の活用などの内容に関連した問題が出題されます。
解答はマークシート方式で試験時間は2時間、100点中70点以上で合格となります。
受験料は6,600円(税込)です。
1級
2級の内容および公式テキストの内容が出題範囲です。
福祉住環境コーディネーター1級の目標と役割、地域で支える高齢者・障がい者ケア、ユニバーサルデザインの概要と沿革、高齢者・要介護者向け住宅・施設の流れ、高齢者住宅・施設や障がい者住宅・施設の種類と機能、福祉住環境コーディネートの実際などの内容に関連した問題が出題されます。
解答はマークシート方式と記述式があり試験時間は各2時間、マークシート方式と記述式各100点中70点以上で合格となります。
受験料は11,000円(税込)です。
福祉住環境コーディネーター試験の難易度と合格率
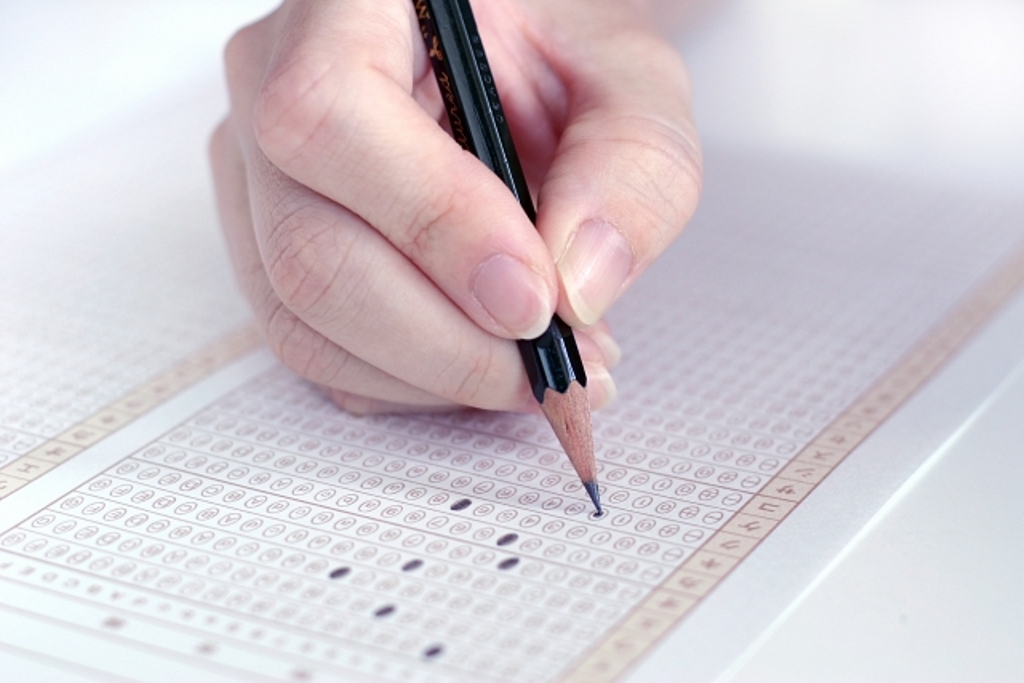
3級は2019年度が58%、2020年度が66.8%で、2級は2019年度が37.7%、2020年度が46.8%でした。
3級は比較的難易度が低めで、公式テキストをひと通り勉強していれば合格可能です。
2級は3級よりも出題範囲が広がり、問題もより専門的な内容になることから難易度が上がります。
2級に合格するには、3級の内容をしっかり復習した上で2級の出題内容をカバーする学習が必要です。
1級は2019年度の合格率が13.8%と狭き門で、難易度が高いです。
マークシート方式だけでなく応用力が必要な記述式の問題も出されるので、出題内容を深く理解するために公式テキストを数回復習する必要があるでしょう。
福祉住環境コーディネーターの将来性

内閣府の発表では、2019年現在の国内の高齢化率は28.4%となっています。
65歳以上の人口が2065年まで増加すると同時に全体人口は減少していくため、高齢化はますます進んでいく見込みです。
高齢者が増えることで高齢者に対応した住環境にしたいという要望が今後も高まることを考えると、福祉住環境コーディネーターの資格を生かした仕事は増え続けるのではないでしょうか。
需要が増えることで給与などの待遇も改善される可能性は高く、福祉住環境コーディネーターの将来性は非常にいいと言えるでしょう。
参考)内閣府 高齢社会白書
おわりに

少子高齢化社会へのシフトにともなって、福祉・介護業界では高齢者や障がい者が住み慣れた自宅で安全かつ快適に暮らせるようサポートしていく流れが強くなっています。
さらに建築業界では、高齢者向けの住宅や住宅型有料老人ホーム等の施設の建築を増やしています。
福祉住環境コーディネーターは誕生してまだ20年余りですが、こうした社会状況の変化によって急速にニーズが高まっている資格であり、これからさらに活躍の場は広がっていくでしょう。
「福祉×介護」についての記事も参考になりますので、ぜひご覧ください