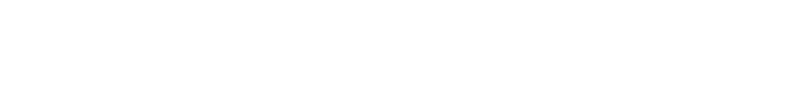
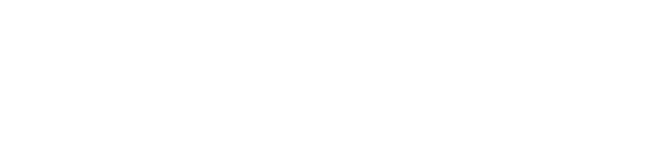
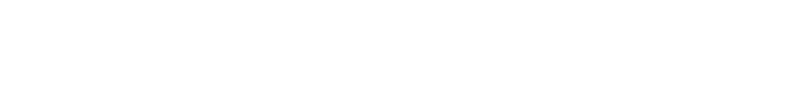
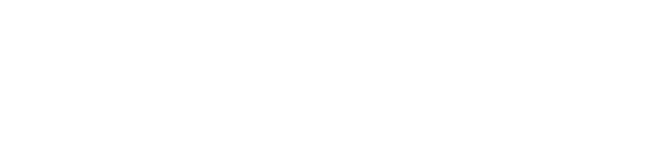



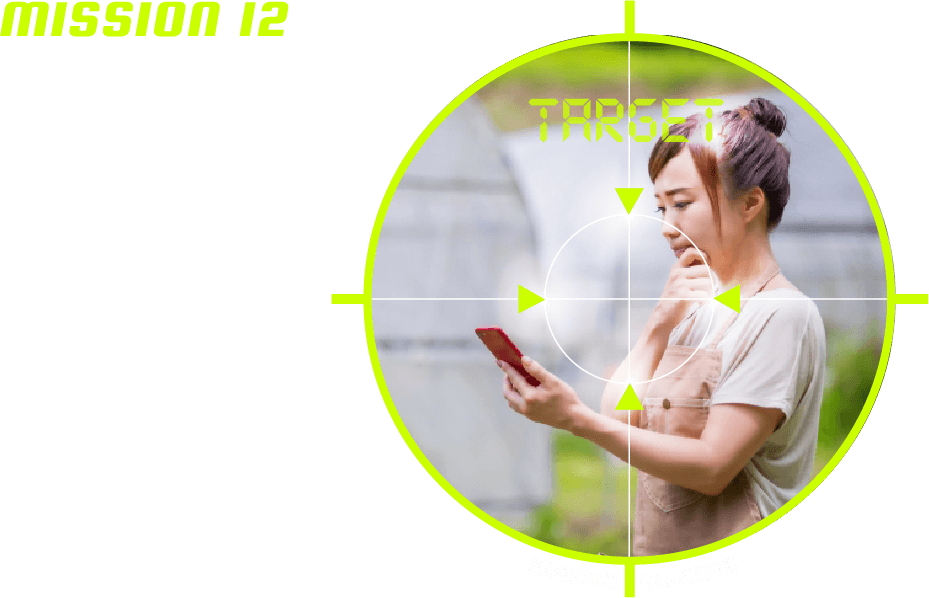

インターネットの普及によって「不要品」
の烙印を押されかけているモノがある。
電話である。固定電話がかつてほどの必要
性を失って久しい。ファクシミリに至っては、
まるでカンブリア紀の化石である。オフィスに横
たわる複合機は、コピー機とプリンタ、スキャナと
しては健在だが、「FAX」のボタンを押したのは何億
年前だったか……。メールやSNSどっぷりのティー
ンエージャーたちからは、「ファックス? それって、おいしいの?」と訊かれる始末だ。
一方で、ネット空間の拡大にともなって「必需品」の太鼓判を押されたモノがある。
電話である。スマートフォンの登場は、社会を一変させた。いまや、世間はスマホなしには機能しない。ハード
としての進化はもちろんだが、目を見張るのはやはりソフトだ。ジャンルと機能に富んだスマートフォンアプリの
増殖ぶりは、多様化しつづける現代社会のニーズの裏返しといえよう。ならば、それに応えぬわけにはいかない。
情報ネットワーク工学科の出番である。




スマートフォンは、いまや若者にとって「友」ともいえる存在である。故に、学生にとってアプリの開発は、ものづくりよりも「友だちづくり」と言えるかもしれない。
自らの技術で創りあげた「友」が社会の抱える課題と向き合い、その解決に貢献できるか。その結果は、工学の道を歩む若者たちに大きな喜びを与えるだろう。そしていま、私たちが課題として取り組んでいるテーマ。それが「安全で豊かな生活への貢献」である。
たとえば、小路口心二准教授のチームでは、
「交通事故発生地点の確認アプリ」を開発している。
交通事故には、さまざまな原因がある。場所や天気はもちろんだが、時間帯も大きく関係しているようだ。そこで、小路口准教授と学生たちは、福岡県が公開している交通事故関連のオープンデータを活用。事故が起きた地点、天気、時間などを抽出し、地図アプリと連動させて可視化した。これによって、出発地から目的地までの〈ルート予報〉が可能となる。つまり、天気予報のような感覚で、事故が起きそうな場所や天気、時間帯を事前に知ることでトラブルを回避するのである。
同じく小路口研究室では、地域で発生する犯罪に着目。これまでに福岡県内で起きた犯罪の「場所をはじめとする諸情報」をマップに表示するアプリを開発した。これが、「福岡県犯罪オープンデータを利用した防犯アプリ」である。
この「可視化」は、アプリ開発のキーワードといえるだろう。では、視覚で伝えられない利用者、つまり眼の不自由な人たちを応援することはできないのだろうか。この問いに答えるのが山田貴裕准教授のチームである。
めざしたのは「点字ブロック認識アプリ」の開発だ。スマホには高性能カメラが搭載されている。この“デジタルの眼”を使って、点字ブロックとその周辺情報をリアルタイムでキャッチ。音や振動によって利用者にブロックの位置や障害物の有無を知らせる。このアプリに期待する声は多いだろう。
情報ネットワーク工学科では、ほかにもさまざまなタイプのソフトに着手。自信作をひっさげて、アプリコンテストやビジネスプランコンテストに挑戦している。
久留米は、古くから先端技術の拠点だった。「からくり儀右衛門」の異名をとった田中久重も、久留米絣を創った井上伝も、当時の最先端を走っていた。彼らがめざしたのも「人々の豊かな暮らし」に貢献する技術であった。
アプリすなわちアプリケーション(application)は、「応用」や「利用」と訳される。同時に、「努力」や「勤勉」といった意味をも有する。確かに、ネットやスマホは暮らしを便利にした。しかし、社会を安心の光で照らし、さらに豊かな未来に導くのは最新の通信インフラや先端のデバイスだけではない。
技術とアイデアをもった若い才能が、時間と汗を惜しまず全力で課題に取り組んでみる。越えられなかったハードルを一つひとつ越えていく。そのひたむきな探究心が次代を拓くのだ。そして、その挑戦の気概こそ、ここ久留米の伝統なのである。