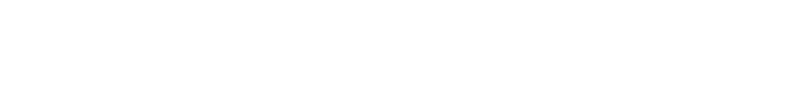
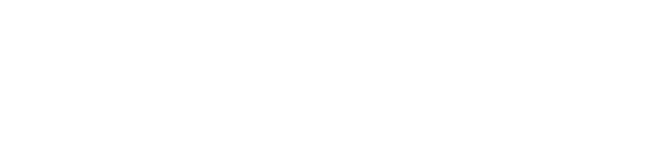
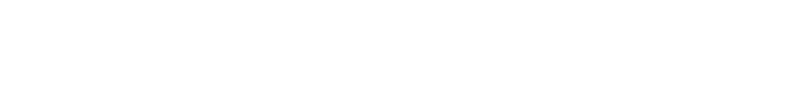
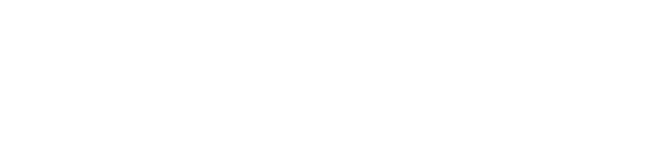



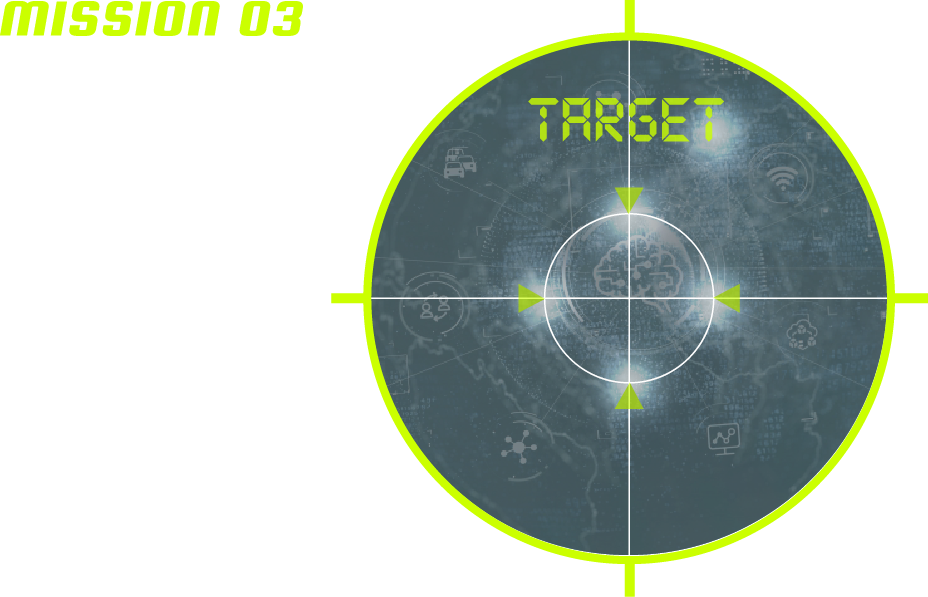

インターネットが地球を覆っている。
パソコンもスマホも、
いまや生活の必需品といっていい。
世界数十億のネットユーザーは、
そのプロフィールも、ライフスタイルや
趣味趣向も、千差万別。そうした個人の志向を基に、
いま、この瞬間にも膨大なデータがやり取りされ、
蓄積されている。
データは、目に見えない。しかしそこには、
無限ともいえる知恵が、経験が、価値が眠っている。
この見えない“宝の山”を、我々の生活に生かせないものか。
この発想から生まれたのが「Code for Kurume」である。





市民が主体となって、ICT(情報通信技術)を活用しながら地域のさまざまな課題を解決する。こうした活動が、いま全国的なムーブメントとなっている。その中心となっているのが2013年に設立された「Code
for Japan」。「ともに考え、ともに作る」をコンセプトに、東京を拠点に幅広い活動を展開している。
「Code for Japan」の理念は、全国各地に広がっており、「Code for ○○」とそれぞれの地名を組み込んだプロジェクトが数多く生まれている。
「Code for Kurume」も、この気運のなかで誕生した。2015年に「Code for
Japan」とも連携し、今日まで活動を続けている。その目的は、ビックデータを活用することによる地域の活性化である。インターネットをとおして自治体や企業は膨大なデータを蓄積している。このデータを公開し、地域の医療や福祉、介護、防災、観光などの各分野に生かすことで人々の生活を豊かにしていくのがねらいだ。
久留米工業大学は、「Code for
Kurume」のコアメンバーとしてこのプロジェクトに参加。情報ネットワーク工学科の教員と学生が中心となり、ICTのスペシャリストとして、システムの開発や運営をリードし、会議やイベント、ワークショップ、報告会などを展開している。