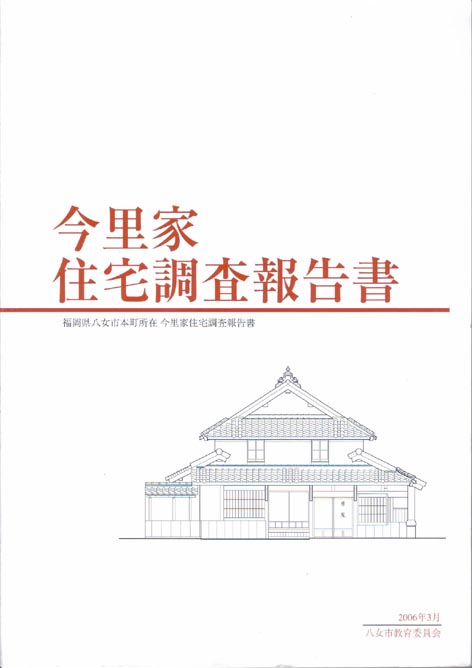「街路とまちづくり」というタイトルで、住民の生活や地域の景観に配慮したみちづくりについて講演を行いました。
イギリスでは、地域の生活や歴史的町並みを護るため、通過交通のためのバイパス道路や環状道路が多く見られます。ところが日本では町のメイン道路が拡幅され生活道路と幹線道路が混同され、その結果歴史的町並みは失われてきました。生活道路のヒューマンな豊かさが取り戻せたらと考えています。
■平成18年5月11日 福岡県街路事業担当職員研修会にて基調講演。
両角先生ご夫妻と一緒に
大森の恩師である熊本大学教授両角先生の還暦を祝う会が熊本で開催されました。還暦といってもまだまだお若く、研究に意欲を燃やされており、私どもは刺激を受けました。久しぶりに研究室の先輩や後輩に会うことができ楽しいひと時でした。
■平成18年5月20日 両角先生の還暦を祝う会 開催
歩行者空間が豊かな
Aix-en-ProvenceのMirabeau通り
かつて並木があった黒木町黒木の旧豊後街道
(写真集筑後黒木より、横溝繁樹氏蔵)
八女福島の町並み
シンポジュームの様子
八千代座内部
旧豊前街道沿いの町並み
熊本県山鹿市は菊池川の水運に恵まれ、農産物の集積地として発展した町です。古来から温泉地としても有名です。今でも旧豊前街道沿いに歴史的町並みが残り、重要文化財の八千代座では芝居や歌舞伎が今でも上演されています。
伝統的建造物群保存地区ではありませんが、街なみ環境整備事業を用いた景観整備が行われています。
■平成18年6月10日 熊本県山鹿市の町並み視察
平成16〜17年度に黒木町黒木の町並み調査(伝統的建造物群保存対策調査)を九州大学の宮本研究室と分担して行いました。その結果を地元の住民の方を対象に報告しました。これからこの黒木の町並みの魅力を住民の皆様と共有してまちづくりにつなげていけたらと思います。
■平成18年8月6日 黒木の町並み調査報告会開催
大学の新入生オリエーテンションで、環境に配慮した建築設備を持つハウステンボスを見学に行きました。あいにくの雨でしたが、コジェネレーションシステムや汚水浄化システム、園内に続く共同溝を見学し、学生は初めて見る建築設備に、これから学ぶ建築設備工学科での学習イメージが少し描けたようでした。
見学後は勿論園内に入場し、それぞれ楽しんでいたようです。
■平成18年4月22日 新入生オリエンテーションでハウステンボスのバックヤード見学
■平成18年6月24〜25日 全国町並みゼミ八女大会プレゼミ開催
10月6〜8年日に、八女市で全国町並みゼミ八女大会が開催されます。それに先立ち、プレゼミが主に九州地区を対象に開催されました。大森もこれからの町並み保存とまちづくりについてのシンポジュームにパネラーとして参加しました。10月の全国大会では全国から歴史的町並みに関わる方々集まり、熱い議論が交わされることを楽しみにしています。
境内のこの空き地に屋台が組み立てられます。
大森研究室の学生も人力車を牽いて祭りに協力しています。
後見役の子供達と役員さんの記念撮影
八女福島で最初の居蔵造である今里家住宅の調査を八女市教育委員会から委託を受け、昨年度実施しました。その調査結果をまとめた報告書を八女市教育委員会から発刊しました。墨書により天保9年の建設といわれていましたが、調査の結果、それ以前に初期の建物は建設されていたことが分かりました。現在は空き家になっていますが、傷みも少なく保存状態も良好で、建物の価値と今後の活用を考え市の文化財となりました。
■平成18年9月1日 八女福島伝統的建造物群保存地区内の今里家住宅調査報告書発刊
大森が伝統的建造物群保存対策調査に参加した鹿島市浜宿が、地区の特性に応じて2地区に分け、国の77番目と78番目の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。浜中町八本木宿は多良往還に沿って白壁土蔵造りの町家や酒蔵が並ぶ宿場町で近世初頭に町が成立しています。浜庄津町浜金屋町は、中世に有明海に注ぐ浜側河口に成立した港町で、近世後期から在方町として発展してきました。茅葺町家が今でも残っています。
■平成18年4月 佐賀県鹿島市浜の中町八本木宿と金屋町が重要伝統的建造物群保存地区に
浄化システムの説明を受ける学生
祭のために組み立てられた燈籠人形の屋台
石垣が観客席に
八女福島の最大の祭である「燈籠人形」が開催されています。「燈籠人形」は江戸時代から続くからくり人形芝居で重要無形民俗文化財にも指定されています。福島八幡宮の境内に屋台と呼ばれる三層からなる舞台小屋が組み立てられ、石垣が観客席に早変りします。戦前までは各町内会で舞台と人形を持ち、毎年当番の町内会が歌舞伎の演目を上演していましたが、戦後は人手不足と資金不足から燈籠人形保存会により上演されています。舞台の両端には3歳から小学生低学年ぐらいまでの子供が人形の後見役として羽織袴の盛装で座っていますが、たまに居眠りして転げ落ちそうになったり、退屈して自主退場したりとそのかわいい姿が祭を盛り上げています。初日の本日は後見役の子供と人形保存会の役員の方々の記念撮影が行われましたが、今年デビューした3歳児たちが並ぶだけで大泣きして、本番で舞台に座っていられるかと家族から心配されておりました。地域コミュニティーに子供をお披露目する儀礼にもなっているようです。
■平成18年9月22日〜24日 福島八幡宮の放生会「燈籠人形」開催
町並みに関心があるまちづくり団体や行政、研究者などが集い研究会を開く町並みゼミが今年は八女市と黒木町で開催されました。一日目は開会セレモニーと岡田文淑氏の基調講演の後は、町並みの種類ごとに分かれた部門別会議や懇親会が行われ、夜更けまで夜なべ談義が続きました。二日目は町歩きと10の研究会が開催されました。大森も黒木町の学びの館で開催された第8研究会「町並み保存と伝建制度の活用」のコーディネーターを担当しました。黒木の町歩きの後は、パネラーやアドヴァイザーの方々や会場を埋めた参加者の皆さんで活発な議論が交わされました。他の研究会も盛会であったようです。三日目は各研究会の報告と「景観法・伝建制度から考える景観づくりと地域まるごと博物館」のパネルディスカッションが行われ、その後大会宣言がなされました。来年は三重県の伊勢河崎で開催予定です。いつもまちづくりを実践されている住民の皆さんの迫力に圧倒されます。
■平成18年10月6日〜8日 全国町並みゼミ八女福島大会が開催
久留米市荒木駅近くのJR線路沿いにレンガ造の工場が並ぶ福徳長酒類があります。大正9年に台湾製糖の工場として建設され戦後福徳長酒類(当時は森永食品)の焼酎製造工場として利用されています。線路沿いに並ぶ切妻屋根の工場をはじめ、事務所棟や樽貯蔵庫、門衛室、倉庫など、多くのレンガ造の建物があります。貴重な近代建築です。
■平成18年11月2日 レンガ造の福徳長酒類工場を見学
旧黒田藩の御用窯であった高取焼きが誕生して今年で400年になります。それを記念してシンポジウムが開催され、大森も文化遺産とまちづくりというテーマでパネラーとして参加しました。高取焼きの登り窯がある高取地区は福岡市副都心の西新の隣にあり、現在はマンションが建ち並ぶ中に立地しています。従って登り窯を使用することができず、この地での存続が危ぶまれている状況です。高取焼きのような貴重な地域の文化遺産をどのようにまちづくりに発展させていくか、今後も継続して検討されるべき課題です。
■平成18年10月29日 高取焼き開窯400年記念シンポジウムに参加
佐賀市内には、茅葺や葦葺き屋根の民家が残っています。先日それらを見学する機会がありました。維持するためには費用がかさみますが、皆さん愛着と誇りを持ってお住まいになっています。ただ、茅葺き職人さんの不足は深刻です。
■平成18年11月16日 佐賀市内の民家
久留米市内の大学や短大、高専では単位互換の授業を行っていますが、1科目だけは各大学の教員が1コマずつ担当する合同講義を中心商店街の中にある講義室「六ツ門大学」でおこなっています。28日は大森の担当で「美しい街に住む」というタイトルで講義をしました。今、美しい景観ということが注目されていますが、どうして今それが求められるようになったのかや美しい町並みはどのように維持されてきたのかなどについて話をしました。景観というものはそこにに暮らす人々の生き方や人生観、そして地域のコミュニティの現状を如実に現しているものだと考えます。どのようなまちづくりをしたいのか、地域の主体的な活動が必要です。
■平成18年10月28日 久留米市内大学合同講義
豆田の町並み
咸宜園の母屋
復原された淡窓の書斎
久留米市中心市街地にある「ほとめき通り商店街」の活性化の提案を学生から募集し、そのプレゼンテーションを行う大会が18日行われました。大森研究室の4年生も応募し見事2位に当たる「ほとめき通り商店街賞」を受賞しました。
彼らは、商店街の空き家や用途調査などを行い、壱番街とその他の商店街との用途による差別化や、壱番街にポケットパークと各大学のサテライトを置く提案を行いました。
■平成18年11月18日 学生まちづくりプレゼンテーション大会で「ほとめき通り商店街賞」受賞
棚田が広がる池の鶴
水にさらした陶土を乾かすかまど
小鹿田焼
福岡市警固公園のクリスマスイルミネーション
大森が町並み保存に関わっている日田市豆田町伝統的建造物群保存地区は、天領時代の商家が並んでいた町で、江戸末期の儒学者広瀬淡窓(1782〜1856年)が誕生した町でもあります。淡窓は豆田町より南へ10分くらい歩いた地に私塾「咸宜園」を開き、身分や年齢に関係なく誰でも受け入れ教育を行っていました。日本でも最大級の塾であったとのこと。現在そこは史跡として整備されています。
■平成18年11月30日 大分県日田市豆田の町並みと咸宜園
日田市には陶器で有名な小鹿田焼があります。先日そこを訪れる機会がありました。陶土を採取している雑木林の山を背景に10軒の窯元があり、陶土作りから窯焼まで全てがほぼ伝統的な工法で行われています。陶土を粉にする唐臼小屋はそれそれの窯元が持ち、登り窯は5軒がそれぞれ1基ずつ、残りの5軒は共同で1基を所有しています。近くには棚田も広がっており、魅力的な景観を見ることができます。
夕日に輝く銀杏
■平成18年12月1日 日田市 小鹿田焼の里
小鹿田焼の里
唐臼小屋
登り窯
元禄蔵と母屋
石橋
水路沿いの景観
■平成18年12月10日 高取焼味楽窯 窯開き
先日、大森がパネラーとして参加した高取焼開窯400年シンポジウムの高取焼味楽窯の窯開きが12月9日、10日開催されました。藤崎商店街裏の丘の中腹にマンションに囲まれて味楽窯があります。その作風は小堀遠州に教えを受けた「きれいさび」が特徴で、茶人に重用されてきました。江戸時代は黒田藩窯として何軒もの窯元が陶器を焼いていたのですが、現在は味楽窯だけが残り伝統を護っています。しかし、周辺環境の変化により登り窯の使用できなくなり、この地での継承が危ぶまれています。地域の大切な文化遺産として、地域住民の理解を得、年2回の登り窯の使用が認められないものかと考えています。
旧唐津街道であった藤崎商店街
商店街に残る伝統家屋の伊佐邸
今年は11中旬まで暖かかったせいか紅葉が遅く、大学構内の銀杏も12月の始めが見ごろになりました。一方街ではクリスマスイルミネーションが輝き始め、紅葉と一緒に見られるという例年にない光景です。イルミネーションは昨年あたりからそれまでの黄色や赤の光から青や白い光が多くなりましたが、これも青色発行ダイオードの発明による効果でしょうか。従来の豆電球に比較し電気代は1/10、寿命は10倍とのこと。
■平成18年12月4日 紅葉とクリスマスイルミネーション
20年ほど前から使用できなくなった登り窯
都心の中で伝統を護る味楽窯の庭園
久留米工業大学 建築・設備学科 大森研究室
旧街道沿いの町家
洋館
田主丸地区近くの屋敷
今年久留米市と合併した田主丸町の中心市街地である田主丸地区には、歴史的町並みが残っています。隣のうきは市にある筑後吉井伝統的建造物群保存地区と同様の旧豊後街道中道に沿って町家が並ぶ在方町です。地区の南には水路が流れ、石積みや石橋、洗い場などが残っています元禄時代に建てられた酒蔵や、洋館もあり、バラエティにとんだ町並み景観が見られます。
■平成18年12月21日 久留米市田主丸の町並み
八女福島のまちづくり団体「ふるさと塾」が年末に開催している「みちばたもちつき大会」が今年も23日に開されました。みんなで協力して餅をつきコミュニティを深めながら地区の老人世帯に正月用の餅を配ろうと始められたもので、誰でも参加でき、毎年場所を変えながら道端で行われています。今年は土橋市場で開催されました。土橋市場は土橋八幡宮の境内に戦後闇市がたち、現在もそのまま鳥居や楼門の向こうに飲食店が並んでいる不思議な空間です。当日は天気にも恵まれ、大勢の参加がありました。餅をちぎる名人や、まるめる名人のおばあちゃんも毎年参加してくださいます。皆さんつきたての餅をおいしそうに食べられておりました。大森研究室の学生も6臼つきましたが、翌日は箸が持てなかったとのこと。皆様お疲れ様でした。
■平成18年12月23日 八女福島の「ふるさと塾」主宰の「みちばたもちつき大会」開催