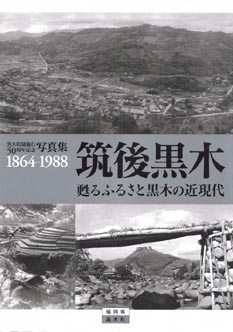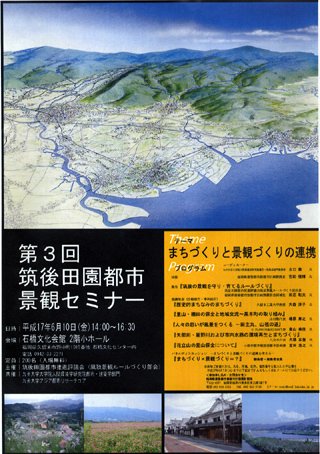■11月17日 福岡県都市公園担当課職員研修会にて基調講演。
■10月22日〜24日 石見銀山調査
九州大学の西山研究室の皆さんと一緒に、世界遺産に登録予定の石見銀山遺跡とその周辺の文化的景観、大森や温泉津の重要伝統的建造物群保存地区の町並み、鳴り砂の琴ヶ浜の保全状況の現地踏査に行きました。踏査の際には、温泉津の町並み保存に関わっていらっしゃる多田先生に案内していただき、多様な文化遺産が存在する石見地方の魅力と地域の取り組みの状況をよく理解することができました。地域の景観の魅力と共に地域を愛するガイドの存在の重要性を実感しました。
■10月 筑後黒木の写真集が刊行
■9月13日〜24日 フランスの文化遺産の保全と活用について視察
パリと南仏プロヴァンス地方の文化遺産の保全と観光活動の状況の視察に行ってきました。プロヴァンス地方には丘の斜面に築かれた昔ながらの景観を残す村が数多くあります。その多くは戦後の人口流出により廃村寸前まで行きましたが、現在は多くの人々がが訪れる観光地になっています。ヒアリングを行った小さなVentabren村では、民宿を営む方が今日は日本人が4人宿泊していると話してくれました。
大森の故郷でもあり現在町並み調査に関わっている福岡県八女郡黒木町の写真集が黒木町教育委員会より発行されました。町民に呼びかけて集められた1864〜1988年の写真が収められており、昔の町の景観や人々の生活の様子が分かります。大森も随想を載せています。一部千円で販売されておりますが、初版の千部はすぐに売り切れ、増刷の予定です。ご興味のある方は黒木町教育委員会にお問い合わせください(リンクのページから黒木町のHPに行くことができます))。
Gordes
エクサンプロヴァンスの緑のコリドール
Ventabren
Ventabren
都市の中に緑の憩いの場を提供しているパリのリュクサンブール公園
岩盤を刻んだ階段
温泉津の町並み
大森の町並み
■10月28日 佐賀県塩田町塩田津が国の重要伝統的建造物群保存地区に選定
2002年〜2003年度に調査を分担し、2005年度に保存計画策定に参加した塩田町塩田津伝統的建造物群保存地区が、国の71番目の重要伝統的建造物群保存地区に選定答申されました。長崎街道の宿駅として、また塩田川に面した川港町として栄えた町で、白壁土蔵造の町家が並び、川岸には土蔵や座蔵も見られます。塩田石の石垣や石像も数多く残っています。
■4月22日 長崎県国見町神代小路が国の69番目の重要伝統的建造物群保存地区に選定
2004年度に調査を分担した国見町神代小路伝統的建造物群保存地区が国の69番目の重要伝統的建造物群保存地区に選定答申されました。17世紀末に鍋島藩の飛び地として陣屋敷と武家町が築かれました。伝統家屋と共に周囲を取り巻く石積み塀や生垣が武家町のたたずまいを残しています。手入れされた生垣の美しさは、ここで暮らす住民の方々の誇りと心意気が窺えます。
■11月19日 久留米市内大学合同講義で「歴史的景観とまちづくり」を講義
久留米市内に立地する大学・高専が合同で開講する講義が本年度より開始されました。受講者は各大学の学生や一般の方で、商店街の中にある六ッ門大学の部屋を使って、各教員が一コマずつ担当しています。本年度は久留米に関することを題材に講義をすることとなりましたので、草野の町並みを中心に久留米市が立地する筑後地方の歴史的景観とまちづくりについて講義を行いました。
久留米市草野の町並み
■7月30日 八女市の「継志塾」で歴史的町並みを観光資源としたまちづくりについて講演
八女市の街づくり団体「八女ふるさと塾」が主宰する「継志塾」において、町並みを観光資源としたまちづくりのあり方と課題について講演を行いました。八女福島重要伝統的建造物群保存地区では、町並みを観光資源としたまちづくりが徐々に進んでいます。空き家の伝統家屋を利用した飲食店も増え始め、観光客も増加しています。
八女福島の横町の通り
■6月10日 筑後田園都市景観セミナーで景観とまちづくりについて基調発表
筑後田園都市推進評議会 風致景観のルールづくり部会(事務局:福岡県)主宰の第3回景観セミナーが「まちづくりと景観づくりの連携」というテーマで石橋文化会館小ホールにて開催されました。
歴史的な町並み景観を保全しながらまちづくりをしている八女福島伝統的建造物群保存地区を事例に、町並み保存とそれを課観光資源としたまちづくりのあり方について発表を行いました。
■11月14日 久留米大学公開講義「市民参加のまちづくり」にて講義
久留米大学経済学部主催で「市民参加のまちづくり」が学生や市民を対象に六ッ門大学で後期に開催されています。7週目が私の担当でしたので、「歴史的環境と観光」というテーマで講義を行いました。文化遺産を保全しそれを活用したまちづくりが全国で模索されていますが、その中でも人々の生活空間である歴史的町並みを観光資源としたまちづくりでは、町並みが持つ文化財としての価値を維持しながら生活環境の向上に努め、観光資源としての価値も高める整備が必要となります。お互いの価値が矛盾しない整備のあり方について講義をしました。
「都市の緑」というタイトルで、都市景観から見た緑の重要性と配置について講演を行いました。都市の中に豊かな緑のコリドールを持つAix-en-Provenceや、市民の憩いの場となっている緑豊かなリュクサンブール公園を持つパリなどを事例に、緑だけではなく建物や看板も含めた一体的な景観コントロールを行わないと緑の効果も少なく、また都市も美しくならないことを発表しました。
■9月27日 福岡国道事務所の懇話会にて発表
歴史的町並み地区のまちづくりにおいてもインフラの整備は重要です。都市を発展させる上でインフラの重要性を最初に認識にその整備に努めたのは古代ローマだと考えます。特に上下水道や道路網の整備にはその技術の高さに驚かされます。当時のインフラに対する考え方や整備状況について話をし、現在の歴史的町並みにも必要であるインフラの整備のあり方と町並み景観との関係について話をしました。
ローマ時代の水道橋 Pont du Gard
アクロポリスの上にサイフォン式の水道により泉を持っていたペルガモン
■3月12日〜22日 トルコの文化遺産とツーリズムの現況を視察
トルコはヒッタイト、古代ギリシャ、古代ローマ、ヴィザンティン、イスラームの各文明の文化遺産が残る魅力的な国です。それらを観光資源とした整備が進められ、観光産業は重要な政策の一つになっています。ただ、イスラーム教徒が国民の99%を占めている現在は、他の文明の文化遺産への関心がそれほど高くないのか、地域住民と文化遺産との関わりがほとんど見られません。ペルガモンやエフェソスは貴重な遺産にもかかわらずなかなか整備が進まず、世界遺産にはまだ登録されていません。
カッパドキアのギョレメの谷では現在もあの奇岩の家に人々が住んでいます。凝灰岩の家は夏涼しく冬暖かで暮らしやすい家だと居住者の方は話してくれました。究極の環境共生住宅ではと思います。もちろん電気や水道などのインフラは整備されています。
エフェソスのセルシウス図書館(145年建設)とハドリアヌス神殿
ヒエラポリスの大通り
ペルガモンのアクロポリスにあるトライアヌス神殿と劇場
カッパドキアのギョレメの谷とパシャバァラルの奇岩
■平成18年1月17日 八女福島の伝統家屋の土壁塗りに小学生が参加
八女福島重要伝統的建造物群保存地区の清田家は現在修理中ですが、土壁塗りに地元福島小学校の6年生全員が参加しました。最初は遠慮がちに壁土を掴んでいましたが、最後は全身泥だらけの児童がたくさん出てくるぐらい熱中していました。
■12月23日 八女福島の伝統家屋がレストランとして再生
八女福島重要伝統的建造物群保存地区内の空き家であった旧金福堂が、フランス料理の店「Kinpuku
Tei」として修理再生され、23日にオープンしました。空き家の利活用が進むことで、町並みが少しずつ賑わいをとりもどしてきています。
修理中の清田家
土壁塗りをしている小学生
修理再生されたKinpuku Tei
■平成18年3月18日 研究室の修士学生の旅立ちを祝う会
■平成18年3月1日〜31日 八女福島のぼんぼり祭(雛祭)開催
伝統家屋の座敷に飾られたお雛様
八女福島で3月中はぼんぼり祭が開催されています。民家の座敷や商家の店の間にお雛様が飾られています。この地方独特のおきあげやさげもんも飾られており、普段は見ることのできない伝統家屋の座敷も公開されています。
白瀬君(修士2年生)の卒業を祝う会を催しました。就職している彼の同級生も駆けつけ久しぶりに八女福島でまちづくり活動をしていた「桃李道(とうりみち)」のメンバーが揃いました。白瀬君が住んでいる町家のオーナーのご好意で土蔵を貸して頂き、伝統家屋が持つ落着いた空間の中で、すばらしい民芸品に囲まれ、贅沢な時間を過ごせました。
八女福島の皆様のおかげで学生達は、まちづくりや伝統的町並みの保全について学ぶことができました。どうもありがとうございました。
久しぶりに揃ったとうりみちのメンバー